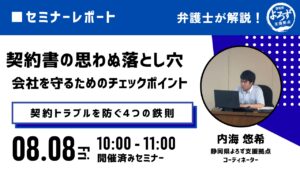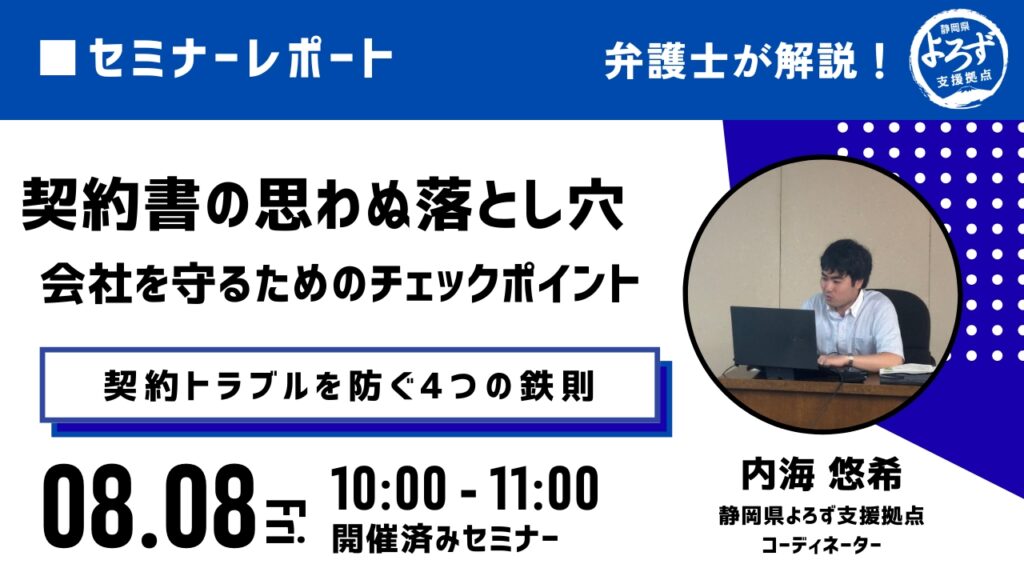
「普段から契約書は交わしているけど、これで万全だろうか?」
「取引先から提示された契約書に、不利な点はないだろうか?」
会社の経営者や担当者であれば、一度はこんな不安を感じたことがあるかもしれません。
先日、静岡県よろず支援拠点では、このようなお悩みを持つ経営者の皆様に向けて、「契約書の落とし穴と対策」と題したセミナーを開催いたしました。講師を務めたのは、当拠点の専門家である内海弁護士です。
ビジネスを取り巻く環境が複雑化する今、契約に関するトラブルは後を絶ちません。今回は、セミナーに参加できなかった皆様にも役立つよう、会社をリスクから守るための契約書の重要ポイントを分かりやすくまとめてお届けします。
専門家が教える!契約トラブルを防ぐ4つの鉄則
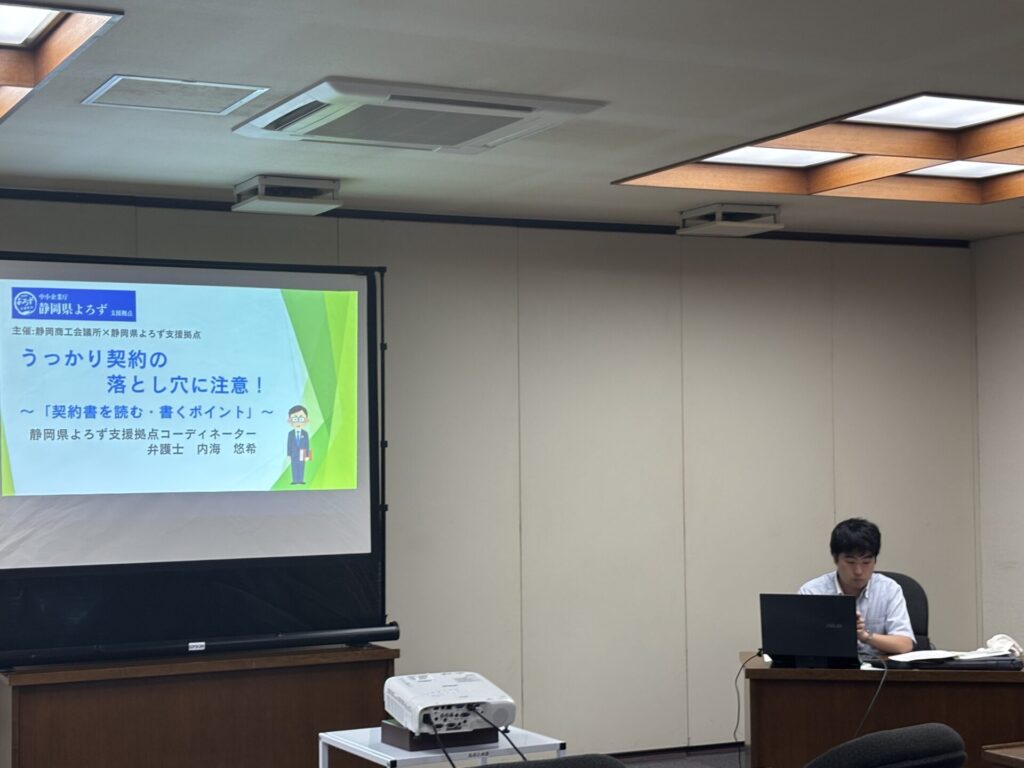
セミナーでは、契約書の基本から具体的なトラブル事例まで、多岐にわたる解説がありましたが、今回は特に経営者の皆様に知っておいていただきたい「最も重要な4つの鉄則」をピックアップしてご紹介します。
鉄則1:なぜ作る?契約書の「2つの目的」を再確認しよう
そもそも、なぜ契約書を作成するのでしょうか?内海弁護士は、その目的を大きく2つあると説明します。
- 証拠としての目的 口約束でも契約は成立しますが、後になって「言った、言わない」のトラブルになることは少なくありません。契約内容を書面に残すことで、誰が、いつ、どのような内容で合意したのかを客観的に証明することができます。メールのやり取りや振込履歴も証拠にはなり得ますが、契約書がある方が圧倒的に確実です。
- 紛争を未然に防ぐ目的 ビジネスでは、予期せぬトラブルが発生することもあります。そんな時に「誰が」「どこまで」責任を負うのかをあらかじめ契約書で明確にしておくことで、いざという時の責任分担をスムーズに決めることができます。これは、無用な争いを避けるための「転ばぬ先の杖」と言えるでしょう。
鉄則2:基本が肝心!契約書の形式チェックリスト
契約書の内容はもちろん重要ですが、形式面にも注意が必要です。後々のトラブルを避けるため、最低限以下の点は必ず確認しましょう。
- 契約締結日は明確に記載されていますか? 「いつ契約したか」は非常に重要です。意外と日付が抜けているケースも多いとのこと。必ず正確な日付を記載しましょう。
- 当事者の署名・押印はありますか? 誰が契約に合意したのかを示す、最も重要な部分です。法人の場合は、代表取締役の記名と、会社の実印があるのが理想です。安易な認印は、後から「勝手に押された」と言われるリスクもゼロではありません。
- 契約書の作成部数は明記されていますか? 「本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印の上、各1通を保有する。」といった一文(後文)を入れることで、お互いが同じ内容の契約書を持っていることを証明し、後から改ざんされるといったリスクを防ぎます。
鉄則3:万が一に備える!必ず入れたい「管轄裁判所」条項
数ある条項の中でも、弁護士目線で特に重要だと指摘されたのが「管轄裁判所」を定める条項です。これは、もし裁判になった場合に、どの裁判所で手続きを行うかを決めておくものです。
なぜこれが重要なのでしょうか? 例えば、静岡の会社が沖縄の会社と取引をする際に、管轄裁判所が「那覇地方裁判所」と指定されていたら、実際に裁判が起こった場合、沖縄まで行かなければなりません。移動費や弁護士の日当など、裁判そのものとは別のところで大きなコストが発生してしまいます。
ここでさらに重要なポイントが、「専属的合意管轄裁判所とする」という一文です。「専属的」と入れることで、「裁判をするなら、絶対にこの裁判所でやります」という意味になり、他の裁判所で訴えられるリスクを無くすことができます。
鉄則4:実例に学ぶ!よくある契約トラブルとその防衛策
セミナーでは、実際に相談が多いトラブル事例も紹介されました。
ケース1:求人サービスなどの「自動更新」トラブル
「期間限定で無料掲載!」といったFAXや電話勧誘で契約したら、気づかないうちに有料の自動更新期間に入っており、高額な請求が来た、というケースです。 対策: まずは安易にお金を払わないことが重要です。相手方は、支払ってしまうと返金が困難になることや、少額なため裁判を起こしにくいことを狙っています。契約の無効を主張し、内容証明郵便で「契約を解除する」「支払いの意思はない」という通知を送るのが有効な手段です。
ケース2:退職した従業員による「顧客の引き抜き」
退職した社員が、競合他社に転職したり独立したりして、自社の顧客情報を利用して営業をかけるケースです。 対策: 就業規則や、退職時に交わす誓約書で、競業(競合する業務を行うこと)を禁止する条項を設けることが考えられます。ただし、職業選択の自由を過度に制限することはできません。「期間(例:退職後1年間)」「地域(例:静岡県内)」「職種」などを具体的に限定することで、有効な定めと認められやすくなります。
まとめ

契約書は、単なる形式的な書類ではありません。ビジネスを円滑に進め、万が一の際に会社と従業員を守るための、非常に重要な「武器」であり「防具」です。
今回のセミナーで紹介されたポイントを参考に、一度、自社で使っている契約書を見直してみてはいかがでしょうか。その一歩が、未来の安心につながるはずです。
静岡県よろず支援拠点では、専門のコーディネーターが無料であなたの経営相談に対応します。一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。